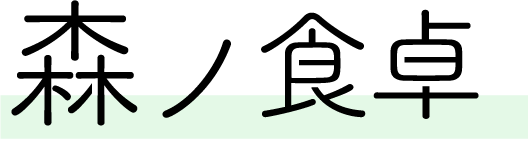ふるさと納税のメリットを知りたい人
ふるさと納税のメリットは?仕組みは?どのように控除される?
3万円を寄付した際の控除額はどれくらい?2000円を差し引くとは?
ふるさと納税の対象者は何税が控除される?
ふるさと税制をした翌年の税金額はどれくらい変わる?
ふるさと納税のメリットをお伝えします。
知ってるけど実際にやったことはない。興味がなかったから詳しく知らない。なんとなく面倒そうだから…
という理由でふるさと納税未経験なら、これからご紹介するメリットをチェックしてください。
目次
ふるさと納税はメリットしかない?5つの魅力を紹介

1.地域の発展や災害支援金として応援できる
ふるさと納税は地域の返礼品を受け取れる他、災害支援金としても活用されます。
災害支援金とは、応援したい自治体の被災地支援を行うお金です。
よく義援金と間違われることもありますが、義援金は直接的に被災者支援に使われます。そのため災害支援金で申し込んだ際は、自治体が対応する台風や地震被害の復興支援に使われます。
例えば令和元年の台風19号支援、令和2年の7月豪雨支援、令和3年の足利市山林火災支援など、日本全国どこからでも被災地を応援できるのです。
2.寄附額に応じた返礼品をもらえる
自治体によって変わりますが、寄附した金額によってさまざまな返礼品を受け取れます。
返礼品の中身は地元特産物であることが多く、野菜や果物、お米や調味料、ご当地キャラグッズや食器類など、幅広い地域の名産品を楽しめるでしょう。
スキンケア用品やタオル類、アクセサリーや認定証もあります。
例えば北海道なら毛ガニ、鹿児島なら焼酎、岩手の南部鉄器も返礼品に含まれます。
ちょっとした日本の味めぐり、旅行先で見つけた伝統工芸品のお土産を手にできるのです。
ただし、1つだけ注意して欲しいのは、ふるさと納税で支援金を申し込んだ場合、寄付金受領証明書は発行されても返礼品はありません。
3.翌年の税金が控除(還付)される
ふるさと納税の控除は、翌年の所得税や住民税で返ってきます。では、流れをご説明しましょう。
- 応援したい自治体に寄付
- 自治体からの寄付金受領証明書を受け取る
- 確定申告
- ふるさと納税した年の所得税が控除される(申請方法により異なる)
- ふるさと納税した年の翌年の住民税が控除される
控除を受けるためには確定申告が必須です。
ふるさと納税を申し込み、自動的に控除されるわけではありません。所得税と住民税の控除対象となる年が違うため、給料明細等を確認し、混同しないよう気をつけてください。
所得税は、ふるさと納税した当年の所得税が控除対象となり、翌年の確定申告後に還付されます。
住民税は翌年6月~翌々年5月までの間、本来であれば必要とされる住民税が減額されます。
所得税のように還付される形ではなく、給料明細や住民税決定通知書を確かめることで、控除を受けたことを実感できるでしょう。
4.ポイントを貯めることができる
ふるさと納税はさまざまな決済方法を選べます。
自治体によってクレジットカード払いにも対応しているため、ふるさと納税で受ける控除にプラスして、クレジットカードのポイントも貯められます。
カード会社によってポイント付与率は異なりますが、通常の通販と同じような感覚で捉えてください。
例えば「楽天」のHPから申し込むふるさと納税では、楽天ポイントの付与を受けられます。
楽天のクレジットカード以外でも問題ありません。他の会社のカードでも決済できますが、楽天のクレジットカードで支払った場合は、少し多めにポイント付与されるケースもあります。
ただし、決済方法は自治体によるため、申し込む前に必ず確認しましょう。
5.寄附額2,000円~始められる
ふるさと納税は、2,000円から始められる寄附です。
「2,000円寄附する」という意味ではなく、収入に応じた限度額はありますが、あとから控除を受けられるので、「自己負担が2,000円で済む」と解釈してください。
「たくさん寄附すれば良い」というわけではなく、限度額を超えた金額は控除対象とはならないので覚えておきましょう。
ふるさと納税の注意しておきたいデメリット
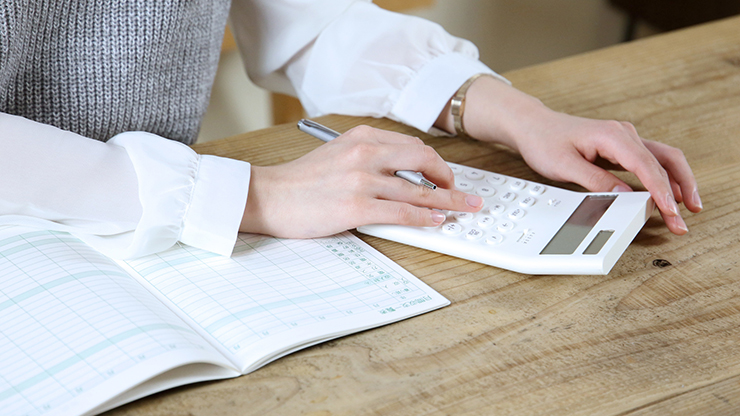
ふるさと納税はメリットだけでなく、デメリットもあります。
デメリットだと感じるポイントは人それぞれですが、申し込む前に確認しておきましょう。
1.節税の対象ではない
ふるさと納税は、節税目的で行うものではありません。
あくまでも自治体への寄附行為。地方の活性化を願って、それに関係する分野へ寄附する形になります。
所得税や住民税の控除を節税と捉える場合もありますが、控除された結果として節税につながるだけです。その証拠として控除限度額はありますが、寄附金額に上限はありません。
つまり控除を受けられる寄附額の上限は決まっていても、それ以上の寄附は何の問題もないわけです。
本来であれば控除を受けられるとか、控除から外れる境界線で寄付金額を判断するのではなく、純粋な寄附行為が理想でしょう。
ただし、それでは多くの人から注目されることはなく、地方の活性化にもつながらないため、控除という形でメリットをつけているだけです。
支払うべき税金が安くなるわけではなく、支払わなければならない税金をふるさと納税へ回す仕組みになります。
2.自己負担2,000円は発生する
お得に特産品の返礼品を受け取れますが、自己負担2,000円は発生します。
そのためふるさと納税で支払う税金に加え、2,000円は自分の所得から支出されます。控除限度額分は控除の恩恵を受けられますが、2,000円分は控除対象になりません。
つまり寄附した金額から控除限度額分の所得税と住民税が控除適用となり、それで相殺されるような状態となります。
しかし、2,000円は適用されないため、自己負担となるわけです。
3.寄附金としての税金は先払い
寄附金でふるさと納税を支払う場合は、手持ちのお金から先に支払う必要があります。
寄附したことを証明しなければならないため、自治体から発行される「寄附金受領証明書」を提示しなければなりません。
例えば会社の経費を使うとき、先に必要なモノを買いレシートを経理に提出します。多くの会社はその経費を確認し、あとからお金が清算される仕組みです。
ふるさと納税もこれと同じような流れで、先に寄附金を支払います。
所得税還付や住民税控除を受けられるのは翌年なので、考えようによっては、寄附した年は大きな出費となるかもしれません。
4.手続きや申請が必要
控除を受けるためには、申請手続きをしなければなりません。
ふるさと納税を申し込んだら自動で手続きが完了するわけではないため、自分で申請する必要があります。
このあたりの仕組みは、行政機関の仕組みを思い出せば心当たりがあるでしょう。
行政機関のさまざまな支援金や手当は、自分から申請しなければ手に入りません。
待っていれば声をかけてもらえるわけではなく、最初は自分で事務手続きを進める必要があるのです。そのため自分の置かれている状況により、確定申告やワンストップ特例制度を利用しましょう。
- 給料所得者(会社員等):ワンストップ特例制度もしくは確定申告
- 個人事業主(自営業)や年金受給者:確定申告(ワンストップ特例制度は利用不可)
- 確定申告の必要ない給料所得者(年間2000万円を超える給料所得者/医療費控除を受ける場合は要確定申告)
- 年間に5つ以上の自治体へふるさと納税を行った(1つの自治体へ5回の寄附は1回としてカウントされる)
- 申し込みごとに自治体へ申請書を送っている
ふるさと納税の詳しい申請方法については以下の記事で紹介しています。
ふるさと納税はするべきか?おすすめできない人は?

多くのメリットを実感できるふるさと納税ですが、この制度をおすすめできない人も存在します。
「こんなにお得なのに?」と思うかもしれませんが、当てはまる場合は申し込みを控えましょう。
給料所得が年間103万以下の人
年収103万以下の人は、ふるさと納税をおすすめできません。
年収103万とはアルバイトやパートなど、所得税が非課税の人です。
ふるさと納税は所得税の還付を受ける形なので、扶養家族に含まれていれば、控除の恩恵を受けられないわけです。
ただし、勤労学生控除を適用されている学生は、年収130万円以下がボーダーラインとなります。
住民税が非課税の人
住民税が非課税の人は、ふるさと納税の控除はありません。
住民税は、一般的に給料所得で年収100万円を超える人が対象と言われています。つまり100万1円になれば、住民税を支払う義務も発生するわけです。
具体的に言えば、扶養家族や未成年者・障害のある方・寡婦・1人親世帯は、前年所得合計が135万以下であれば非課税です。
ただし、住民税は住んでいる自治体によって違うため、自分の住民税を詳しく知りたい人は自治体に確認してください。
ふるさと納税には住民税の控除があります。それが非課税となっている場合は控除の対象とならないため、ふるさと納税をおすすめできません。
公的年金収入のみで245万円以下の人
公的年金245万円以下の収入で暮らす人は非課税です。公的年金は雑所得に含まれますが、年金額が年間245万円以下の場合は非課税対象者なので、ふるさと納税の恩恵は受けられません。
4,000円以上のお金を担保できない人
手持ちのお金が少ない人は、ふるさと納税をおすすめできません。
ふるさと納税は先に寄附金を支払わなければならないため、4,000円以上のお金を担保できないなら、辞めておきましょう。寄附金3,000円以内は、購入可能なモノも多くありません。
返礼品なしなら、1,000円から受付けている自治体もあります。4,000円以上なら置物や備長炭、タオルやお菓子など、選択肢の幅も広がります。
そのため4,000円以上の手持ちがないなら、ふるさと納税を控えたほうが良いでしょう。「絶対に辞めたほうが良い」という意味ではありません。
自由に使えるお金が3,500円あったとして、2,000円のふるさと納税に申し込んだとします。
ただし、残りの1,500円で過ごさなければならなくなり、友人との外食を我慢する事態も否定できません。
他にも支払いが集中したり、出費が重なって手持ちの現金に不安があるようなら、次回へ見送ったほうが良いでしょう。
対象者はお得!豪華な返礼品をゲットしよう

控除の対象になら、ふるさと納税に申し込んで返礼品をもらいましょう。
返礼品には豪華なモノを用意している自治体もあり、場合によっては通常なら難しい特典も受けられるかもしれません。
返礼品還元率は100%越えのものも!
返礼品は自治体により違いますが、還元率は100%を超えるモノもあります。
例えば焼き肉やすき焼き用の伊万里牛肉800gであれば、15,000円の寄附金で116%。四万十ひすい餃子かつお餃子であれば、15,000円の寄附金で103.2%に還元率が見込まれます。
還元率が表示されたHPもあるため、気になる人はお目当てのモノを確認しても良いでしょう。
ワンストップ特例制度で確定申告は不要!
ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告の必要はありません。
封筒や切手、ワンストップ特例制度申請用紙、本人確認書類を用意してください。
HPから申し込んだ場合は申請書をダウンロードできる場合があり、自治体によっては寄附金受領証明書に同封されるケースもあります。
必要な書類等が準備できたら、翌年1月10日までに必着するよう郵便で送りしょう。
これだけで確定申告は不要です。個人事業主はこの制度を利用できないので、確定申告の手続きを確認しましょう。
まとめ
- 災害支援金として寄附可能
- ポイントを貯められる
- 寄附金は先払い
- 還元率100%超えもある
- 自己負担2,000円から利用できる
住民税非課税世帯は控除を受けられません。
また、手持ちのお金が少なければふるさと納税をおすすめできませんが、誰でも寄附できるメリットの多い仕組みなので、控除対象の人は申し込んでみましょう。
自治体が用意する返礼品は…。とネガティブなイメージも先行しがちですが、ふるさと納税に限ってそれは当てはまりません。
品質の良い野菜や肉、伝統工芸品やアクセサリーなど、ご当地自慢の一品が提供されています。所得税や住民税の控除も受けられるため、利用しない手はないでしょう。