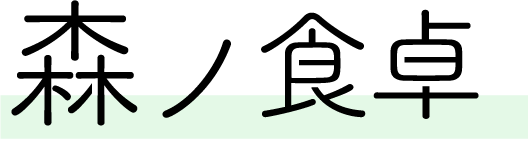ふるさと納税の申告を省きたい人
ふるさと納税を申告しないと寄附金控除がされない?
確定申告なしのワンストップ特例制度とは?
ワンストップ対象者の条件は?申告不要にする手続きは?
ここ数年でふるさと納税が急に流行り始めてきました。実際にこの制度を利用している方も多いのではないでしょうか。
そんな中で「確定申告をしなければならないけどやり方が分からない」という人も沢山いるでしょう。
ここでは、そんな方たちのために確定申告の方法や必要なもの、ワンストップ特例や確定申告の時期等をお伝えしています。
各章に分けて分かりやすく書いてありますので、きっと確定申告の悩み疑問を解消できます。確定申告をしなかったり、不備があったりするとせっかくお得な制度であるふるさと納税を利用しても損してしまうことがあるので、一緒にしっかり学んでいきましょう。
目次
確定申告不要のふるさと納税ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税の確定申告をやるうえで、ワンストップ特例という言葉を目にした方もいらっしゃると思います。言葉を見ただけではなんのことかさっぱりわからない方も多いでしょう。
ここではそんなワンストップ特例制度について詳しく見ていきます。
確定申告が不要になる制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者(仕事の対価としてお金を貰っている人)がふるさと納税をおこなう場合、確定申告をせずにふるさと納税の寄附金控除(寄附をすると税金の支払いが少なくなる)が受けられるものです。
- ふるさと納税をした自治体が5個以内
- ふるさと納税を行う際に自治体1つ1つにワンストップ特例の適用に関する申請書を提出する
といった条件があります。
ふるさと納税をした自治体が自動的にやってくれるものではないので、特に2つめの項目は忘れないようにしましょう。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、ふるさと納税をした翌年6月以降に発生する住民税の減額という方法で控除(ある金額から差し引くこと)が行われます。
所得税からの控除ではないところは注意です。
確定申告とワンストップ特例の併用は不可能
確定申告よりも簡単なワンストップ特例制度ですが、1つ注意が必要なことがあります。
それは、確定申告をするとワンストップ特例制度が無効になるということです。
例えば、5団体(ふるさと納税の場合は市区町村など)以内のふるさと納税予定でワンストップ特例制度の申請をしていたが、最終的に10団体まで増えて確定申告をした場合、申請していた5団体のワンストップ特例制度は無かったことになります。
その場合は申請していた5団体の分も含めてふるさと納税の寄附金控除を申請してください。
改めて申請しない場合は、還付、控除の対象になりませんので注意しましょう。
もともと確定申告が不必要な人
確定申告が不必要な人はどんな人か見てみましょう。
- 年収2000万以下で会社からの給与以外に収入がない
- 会社から源泉徴収をされている
- 会社が年末調整をしてくれている
また、副業などで稼いだ会社以外からの収入があっても、20万円以下なら不要な場合があります。
簡単に言うと、法令で定められている確定申告をするべき人の条件に当てはまらない人ということになります。
源泉徴収とは会社が、1カ月の給与から年間にかかる大体の所得税を天引きして代わりに納めてくれる制度のことです。
それに関係する年末調整は、従業員が納めるべき所得税と源泉徴収としてあらかじめ引かれた所得税額の過不足を会社が調整してくれる手続きです。
年末調整、源泉徴収は会社が代わりに所得税関連の手続きをしてくれる制度、確定申告は自分で税金を申告し支払う制度と覚えておきましょう。
確定申告とワンストップ特例制度はどっちがお得
確定申告とワンストップ特例制度は計算方法と、控除される税金が違います。
- 確定申告によるふるさと納税は所得税からの控除
- ワンストップ特例制度では住民税からの控除
ちなみにワンストップ特例制度の方がお得になることがあります。
それは、住宅ローン減税と併用する場合です。
住宅ローン減税は所得税から控除しきれない部分を住民税から控除するのですが、住民税には住宅ローン減税の上限が設定されています。
確定申告で併用した場合、所得税の計算はふるさと納税の控除が優先されるため、所得税から住宅ローン減税分が控除しきれなくなってしまうことがあるのです。控除されない分は住民税から控除されますが、上限を超えてしまうことがあり損してしまうことになります。
ワンストップ特例制度は住民税から控除する制度ですので、住宅ローン減税の控除枠が大きくなるのです。
以上を踏まえると、住宅ローン減税の金額が大きい人はワンストップ特例制度のほうがお得になるでしょう。
確定申告の方法は結構複雑ですし、上記の理由からもともと確定申告がいらない人は時間と労力だけ見てもワンストップ特例制度を利用する方がお得といえます。
ふるさと納税の確定申告

ここでは、ふるさと納税の確定申告が必要な人の条件を学んでいきます。
結構複雑なのでしっかり理解していきましょう。
そもそも確定申告とは
先にも述べましたが、簡単に言うと1年間で得た収入を申告し税金を納める制度です。
申告忘れや、わざと申告しなかった場合ペナルティや、悪質なものだと逮捕されることがあるのできちんとした知識を身に付けましょう。
ふるさと納税の確定申告が必要な人
ふるさと納税の確定申告が必要な人は、6個以上の自治体にふるさと納税をしている、かつ、もともと確定申告が不必要な人の項目内にある確定申告が必要な人の条件欄にあてはまる人のことを言います。
ここで確定申告が必要な人はどんな人か見ていきましょう。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 自営業、フリーランス、個人事業主で事業収入がある人
- 一定額の公的年金を受け取っている人
- 不動産や株取引などの、その他収入がある人
などのに当てはまる人は確定申告が必要です。
ふるさと納税の確定申告で必要なもの

ふるさと納税の確定申告には用意するものが多々あります。正しく確実な申告のためにしっかり必要なものをここで確認していきましょう。
寄附金受領証明書
寄附金受領証明書とは、特定団体(慈善団体、市区町村等)に対して寄附を行ったことを証明するものです。身近なもので言うと商品を購入したときにもらう領収書と同じような効力を持ちます。
そして、この証明書が送られてくるタイミングは各自治体によって違うので、届くのが遅いようであれば納税先の自治体に問い合わせてみましょう。
ちなみに紛失すると再発行してくれない自治体もありますし、再発行も時間がかかりますので紛失には気を付けましょう。
源泉徴収票
源泉徴収票は、会社から支払われた給与総額と、そこから社会保険料や所得税が引かれた金額がまとめられている書類です。
一般的には12月に交付され、所得税法では翌年の1月31日までに交付しなければならないとされています。
年の途中に退職した場合は退職後1カ月以内が期限です。万が一送られてきていない人は催促してください。確定申告で収入等を記載するのに必要となってくるので、会社からもらったら無くさないようにしましょう。
個人事業主の場合は、自分が源泉徴収されているか・いないかを分かるように確認しておいてください。
還付金の受け取り口座
原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協働組合および漁業協働組合の預金口座が指定できます。
なお、一部インターネット銀行は振込指定できないものがあるのでご利用のインターネット銀行でご確認してください。
また、確定申告者本人の名義口座でないと利用はできません。本人名義の他に屋号(会社の名前)などが入っていると振込されないことがあるので注意してください。
マイナンバー(個人番号が分かるもの)
マイナンバーがわかれば大丈夫です。この場合は、個人番号の通知カードやマイナンバーカードでマイナンバーは確認できます。
印鑑
ここで言う印鑑は、実印でなくてもかまいません。
銀行印や三文判等の認印でも確定申告に使用できます。しかし、インクのいらないシャチハタは使えません。
また、申告者の姓名の含まれていない印鑑、屋号のみの印鑑は使用不可です。
ふるさと納税は確定申告の2か所に記入

ここでは、ふるさと納税の確定申告記入方法を紹介していきます。2か所に記入すればよく、とてもわかりやすいので頑張っていきましょう。
税務署や国税庁のホームページで確定申告を入手
まずは確定申告書を手に入れましょう。
- 国税庁ホームページに掲載されているので必要なものを印刷する
- 税務署や確定申告会場、市区町村の担当窓口や指導相談会場で入手
どちらかの方法で入手できます。
また、確定申告の際ホームページ上でも確定申告書が作れるように専用サイトを国税庁が用意していますので、そちらを利用するのも良いでしょう。
1.寄附先の名称、金額を記入する
確定申告Aの第二表「寄附先の名称等」という欄と「寄附金」の欄に記入してください。
自治体から送られてきた寄附金受領証明書を見ながら正確に記入しましょう。
2.寄附金控除額を計算して記入する
次は、確定申告書Aの第一表に記入していきます。
「寄付金額から2000円を引いた金額」か「総所得金額×0.4」のどちらか少ない方の金額を「寄附金控除」に記入してください。
記入が終わったら寄附金受領証明書をの台紙に張り付けて完了です。
確定申告の提出方法

確定申告の提出方法はいくつかあります。紹介する方法で自分がやりやすい方法を選び確実に提出しましょう。
郵送して提出する
郵送の場合、確定申告書が完成したら封筒に書類を入れ自分の住所地所轄の税務署に送付しましょう。
大切な書類ですので簡易書留を推奨致します。
税務署の専用窓口に持参する
持参するのは面倒ですが、不安を感じる人は提出前に相談ができ、再提出やペナルティを防ぐことができるのでおすすめです。
しかし、申告期間中はかなり混雑しているので忙しい人には向かない方法かもしれません。郵送時のトラブルだけが心配な方は、税務署の時間外収受箱への投函による提出も可能です。
e-TAXを使ってインターネット上で提出する
最近は、国税庁もこのインターネット提出を推奨しています。
24時間提出可能で、作成の際に困ったことがあれば電話質問対応してくれる窓口も用意されていて便利です。(窓口は24時間ではありません)
こちらの提出法には、マイナンバーカード方式とID・パスポート方式があります。
マイナンバーカード方式には、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。ICカードリーダライタは家電量販店で購入ができます。また、代わりにマイナンバーカード対応のスマートフォンも使用可能です。
ID・パスポート方式では、ID・パスポート方式の届出が必要になります。届出は、税務署で届出する方法と家から届出する方法があります。家で届出するには、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要なので税務署に行ったときについでに届けるのがおすすすめです。
ふるさと納税の確定申告に関するQ&A
ふるさと納税きっかけで初めて確定申告する人も多いでしょう。
そんな時に疑問に思うことは多々あると思います。ここではそんな疑問を解決していきます。
Q
確定申告の期間はいつから、いつまで?
A
毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に申告する決まりとなっています。ちなみに令和2年度分の確定申告は、緊急事態宣言の影響で4月15日までとなっていました。
Q
確定申告をしないとどうなる?
A
ふるさと納税は寄附した金額がそのまま返ってくる訳ではなく、住民税、所得税から控除される形で返ってくるので申請しなければもちろん控除は受けられません。
Q
確定申告を忘れてしまった
A
忘れてしまったらすぐに期限後申告をしましょう。
しかし、期限後に申告しても残念ながらペナルティが発生してしまいます。
令和3年1月1日以降は原則として期限翌日から2月経過まで年7.3%の延滞税か延滞税特例基準割合+1%のどちらか低い方が基準です。(具体的な割合は令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は年2.5%)
2月以降は年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のどちらか低い方になります。(具体的な割合は令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は年8.8%)ですので、期限後申告は早ければ早いほど傷が浅くて済みます。
Q
ワンストップ特例制度と確定申告を併用してしまった
A
確定申告をした場合、ワンストップ特例制度は無効です。
そうなった場合は、ワンストップ特例制度を利用した分の確定申告も改めてしましょう。
おそらく気づいたころには、確定申告をした後でしょうから、すぐに「訂正申告」をすることをおすすめします。期限内であれば特にペナルティもなく申告できます。
手続きの方法はもう一度確定申告をやり直せばいいだけです。
同一人物が2つ以上の確定申告をした場合、税務署は最後に提出されたものを正式なものとして取り扱います。
Q
税金が控除される時期はいつ?
A
実際に確定申告を行い税金が控除される時期は、ワンストップ特例制度利用の場合、住民税からの控除となるので確定申告した年の6月以降です。
確定申告をした場合は、申告する年度の所得税から控除されます。
まとめ
以上、この記事ではふるさと納税の確定申告について
- 自分が確定申告するべきか、ワンストップ特例制度を利用すべきか
- 確定申告で必要なもの
- 確定申告の方法
- 確定申告の提出方法
- 確定申告時に出るお悩み
が学べたと思います。
ふるさと納税の確定申告は一見すると難しそうですが、通常の確定申告に加えて2か所余計に記入し、必要書類を添付するだけなのでそこまで複雑なものではなさそうです。
しっかりと調べながらやればどなたでもできると思います。ふるさと納税はお得な制度ですから積極的に利用し、確定申告を正しくして税金の優遇を受けることをおすすめします。
さらに、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告無しで税金がお得になりますので、面倒そう難しそうという理由だけで敬遠するのはもったいないですよ。